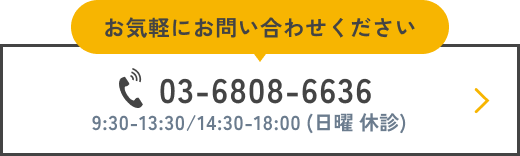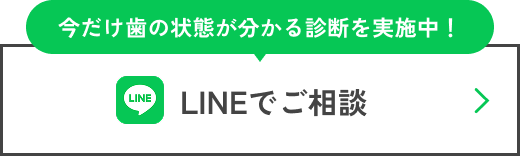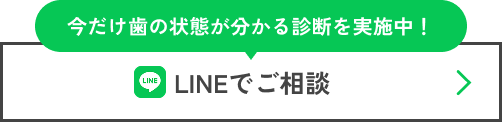歯ぎしりの癖がある人のマウスピース矯正は可能?影響と注意点を解説

マウスピース矯正は、目立ちにくく取り外しができるため、希望されることのある矯正方法のひとつです。しかし「歯ぎしりの癖があるけれど、マウスピース矯正を受けても大丈夫だろうか」と不安に感じている方も少なくありません。歯ぎしりは無意識のうちに強い力がかかるため、矯正治療や口腔内の状態に影響することがあります。今回は、歯ぎしりの癖がある人がマウスピース矯正を受ける場合にどのような影響があるのか、注意すべきポイントや矯正方法の選び方について解説します。
SUPERVISOR
この記事の監修者
日本歯周病学会認定医
大学病院の歯周病科で10年以上にわたり研鑽を積み、海外の歯周病・インプラント学会でも発表を重ねてきました。
「歯を抜かずに残す」治療を追求し、矯正や補綴、咬み合わせ診断を組み合わせた包括的なアプローチで、再治療のいらない安定した口腔環境を目指しています。
口腔内写真やデジタルレントゲンを活用し、わずかな変化も見逃さず管理。いびき治療や栄養・ストレッチ指導など生活習慣にも踏み込み、全身の健康寿命を延ばすサポートを行っています。
海外で得た最新知見も診療に即反映し、長く健康な口腔状態を維持できるよう努めています。
▼目次
1. 歯ぎしりがマウスピース矯正に与える影響とは

歯ぎしりとは、睡眠中や無意識のうちに上下の歯を強くこすり合わせたり、食いしばったりする習慣のことを指します。強い力が歯や顎に加わることで、さまざまな影響を及ぼすことがあります。マウスピース矯正中に歯ぎしりがある場合、以下のような影響が考えられます。
(1)マウスピースの破損や変形のリスク
マウスピースは柔軟性のあるプラスチック素材で作られており、過度な圧力や摩擦によってひび割れや変形が起こる場合があります。歯ぎしりが強い方では、作り直しが必要になるケースもあります。
(2)矯正力が働きにくくなるケース
マウスピースは歯に一定の力を加えて動かしていく装置ですが、歯ぎしりによって想定外の力が加わると、矯正力がうまく働かず、歯の移動が予定通りに進まないことがあります。
(3)顎関節への負担
歯ぎしりにより、顎関節に大きな負荷がかかる場合があります。マウスピース矯正中は噛み合わせが変化するため、顎の関節に痛みや違和感が生じやすくなることがあります。
(4)歯のすり減りや知覚過敏
歯ぎしりによって歯の表面がすり減ると、象牙質(歯の内側にある層)が露出して知覚過敏を引き起こすことがあります。マウスピースを装着することである程度、歯は保護されますが、歯の負担は完全には防げないこともあります。
(5)マウスピースの装着時間が短くなる可能性
違和感や破損が原因で、マウスピースの再作成が必要になると、その間は装着できない期間が生じる場合があります。装着時間が不足すると、治療効果に影響する可能性があります。
マウスピース矯正を検討している方は、歯ぎしりの有無を事前に歯科医師に伝え、十分な相談を行うことが重要です。
2. 歯ぎしりのある人がマウスピース矯正を受ける際の注意点

歯ぎしりの癖がある方がマウスピース矯正を受ける場合には、事前の準備や日常生活での工夫が求められます。マウスピース矯正を受ける際の注意点を解説します。
(1)歯ぎしりの癖を必ず申告する
初診のカウンセリングで歯ぎしりがあることを伝えることは重要です。歯科医師が治療計画や装置の強度を工夫し、リスクを減らすことにつながります。
(2)装着時間が不足しやすい
破損を恐れて外す時間が増えると、治療の進行が遅れる原因となります。歯ぎしりがある人は特に装着時間を意識することが重要です。
(3)歯や顎にかかる負担
歯ぎしりは歯や顎関節に大きな力をかけるため、矯正中に痛みや不快感が増すことがあります。場合によっては顎関節症の症状が出ることもあります。
(4)追加のマウスピースが必要になる場合
破損や摩耗により予定外に新しいマウスピースを作り直すことがあり、治療期間や費用が増える可能性があります。
(5)ストレスケアを意識する
歯ぎしりはストレスと密接な関係があるとされており、日常的なストレスの軽減も予防策のひとつです。十分な睡眠、食生活の改善、リラクゼーションなどを取り入れてみましょう。
歯ぎしりがあるからといってマウスピース矯正をあきらめる必要はありませんが、これらの注意点を守ることが大切です。
3. 歯ぎしりの癖がある人に適した矯正方法の選び方

歯ぎしりがある方にとって、マウスピース矯正が適しているかどうかは、個々の状態や生活習慣によって異なります。歯科医師との十分な相談をもとに、自分にとって無理のない矯正方法を選ぶことが重要です。
(1)マウスピース矯正は条件付きで選択可能
歯ぎしりが軽度で、歯や顎に大きな負担がなければマウスピース矯正も検討できます。ただし、装置が破損しやすいため歯科医師の判断が欠かせません。
(2)ワイヤー矯正は強度に優れる
固定式のワイヤー矯正は装置自体が壊れにくく、歯ぎしりの影響を受けにくいというメリットがあります。長期間の装置装着が必要ですが、治療の安定性を重視したい人に向いています。
(3)部分矯正という選択肢
歯並び全体ではなく一部を整える場合は、部分矯正で負担を軽減できることがあります。歯ぎしりの程度や症状に応じて取り入れられる方法です。
(4)治療計画を柔軟に調整する
歯ぎしりの強さや症状の変化に応じて、矯正装置の調整や治療期間の見直しが必要になることもあります。継続的に歯科医師と相談することが大切です。
矯正方法は一人ひとり異なるため、自分に合った方法を見つけることが納得のいく治療結果につながるでしょう。
4. 江戸川区葛西の歯医者「葛西駅前あなたの歯医者さん矯正歯科」のマウスピース矯正(インビザライン)

葛西駅前あなたの歯医者さん矯正歯科は、東京メトロ東西線「葛西駅」から徒歩2分、西葛西駅からも徒歩圏内にある歯科医院です。
月曜〜土曜の9:30〜18:00まで診療しており、地域に根ざした丁寧な診療を心がけています。
当院では、目立ちにくく、取り外し可能なマウスピース型矯正装置「インビザライン」による矯正治療をご提供しています。ワイヤーやブラケットを使用しないため、見た目や日常生活への影響を抑えたい方に選ばれやすい治療法のひとつです。
当院のマウスピース型矯正(インビザライン)の特徴
(1)精密な検査と3Dシミュレーション
歯科用CTや口腔内スキャナーを用いて、歯の位置や骨の状態を立体的に把握。3Dシミュレーションにより、治療のステップを事前に確認しながら進めることができます。
(2)豊富な症例に基づいた治療提案
当院では、一定の治療実績が認められた医院にのみ与えられる「インビザライン プラチナエリート」の称号を取得しており、さまざまな歯並びのお悩みに対応してきました。これまでの症例をふまえ、患者さんに合った治療計画をご提案いたします。
(3)小児矯正にも対応
子ども向けには、成長段階に合わせた「インビザライン・ファースト」にも対応しております。歯の生え変わり時期に適した矯正治療をご案内しています。
(4)通いやすい立地と診療体制
「葛西駅」から徒歩2分という立地に加え、土曜診療も行っています。
お忙しい方でも無理なく通院できる環境づくり、お子さま連れの患者さんにも配慮した院内環境づくりを行っています。
矯正治療をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。現在のお口の状態や矯正治療の選択肢について、わかりやすく丁寧にご説明いたします。
まとめ
歯ぎしりの癖がある方でも、マウスピース矯正を行える場合もありますが、事前の診断が重要です。装置の破損や矯正力の影響といったリスクもあるため、装置の選び方、生活習慣の見直しなどが必要になるケースもあります。歯ぎしりの程度や口腔内の状態に応じて、マウスピース矯正に限らず他の方法を提案されることもあります。江戸川区葛西駅前周辺でマウスピース矯正についてお悩みの方は葛西駅前あなたの歯医者さん矯正歯科までお問い合わせください。
監修ドクター

医療法人社団 YOURDENT
理事長 久保田達也
歯学博士(Ph.D.)、歯科医師(D.D.S.)、デジタルコンテンツマネジメント修士
運営クリニック
・葛西駅前 あなたの歯医者さん 矯正歯科
・葛西駅前 君の歯を残したい歯医者さん 歯科・矯正歯科
略歴
・日本大学歯学部 卒業
・日本大学歯学部大学院 修了(骨粗鬆症および再生治療に関する研究)
-First Authorとして英文論文4本を執筆
・デジタルハリウッド大学院 修了(デジタルコンテンツマネジメント修士)
スタディグループ
日本歯周病学会 認定医
日本臨床歯周病学会
日本口腔インプラント学会
Osseointegration Study Club of Japan
日本顎咬合学会(咬み合わせの学会)
日本抗加齢医学会(アンチエイジングの学会)
国際歯周内科学研究会
歯科機能性医学研究会
所属学会・認定資格
分子栄養学研究所
大森塾 東京 第一期
情熱会
ENの会
THREEE. 理事
小児歯科実践塾
K-project
TS study Club
PaDaWaN_DSG
臨床基礎蓄積会 副会長
Jiads Study Club Tokyo
川口ぺリオインプラント研究会
つかだ矯正勉強会
INTERDISCIPLINARY TEAM IN DENTISTRY
JIADS東京
葛西駅前あなたの歯医者さん矯正歯科
※「葛西駅前あなたの歯医者さん矯正歯科」で希望日のご予約ができない場合、下記「君の歯を残したい歯医者さん」のご予約をご検討ください。
葛西駅前 君の歯を残したい歯医者さん 歯科•矯正歯科
治療方法の選択は、見た目や生活スタイルの優先度に応じて検討することが大切です。